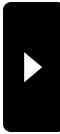2014年10月13日
再エネに冷や水浴びせる電力会社の契約中断

再エネに冷や水浴びせる電力会社の契約中断 太陽光発電の買い取りを止めた九州電力
日本の既存大手電力会社は、再生可能エネルギーよりも原発再稼働優先がホンネですので、電力自由化の法律整備までに、ライバルに成りそうな会社を叩いて置くつもりでしょうが、これこそ先を見通せていない場当たり的な経営戦略です。会社の内外に対して成るほどと納得できる方針を提示する必要が有ると思います。
既存電力会社が自らのイノベーションにより、再生可能エネルギー発電の有効な取組を行わずに目先の利益目的で原発を再稼働していると、莫大な原発不良債権のつけ回しはますます膨らみ、例え事故が起こらなくても何れ経営を圧迫するでしょう。近いうちに電力自由化は始まりますし、このままでは既存電力会社の株価は、大きく値下がりする事でしょう。
既存電力会社の経営陣の方々には、日本国内の電力事業の利権を守る事だけを考えないで、世界の流れをよくよく見て欲しいものです。大きな流れはどんどん遣って来ています。もう鎖国制度が成り立つ時代ではないと思いますよ。
2014年09月26日
「取引士」に改称/宅建業法改正案/主任者の地位向上


昨日は、(公社)鹿児島県宅建協会の業者研修に参加して、民法改正に伴う重要事項説明のポイントに付いて学びました。特に注意が必要なことは、すでに施工済みの消費者契約法に関連する事と、自然災害や地質地歴に関する事項、そして瑕疵担保負担の取り扱いに関する事項でした。
特に近年強化された瑕疵に該当する事項では、物件そのものではなく契約当事者の反社会的勢力(暴力団やテロリストやカルト教団など)への加盟もしくは、反社会的勢力への不動産供与に関する排除命令に対する違反行為についての、厳しい契約解除もしくは損害賠償請求権の特約措置に付いてです。
日本では、従来、社会的通念や性善説による信義信頼を基に、契約書面による表現が比較的に緩やかで簡素化されていましたが、人の交流や経済の国際化が進んでいる現在は、欧米型の社会契約主義に遵守せざる負えない現状が有りますので、重要事項説明及び契約締結を行う際には、消費者保護とトラブルを未然に防ぐ目的として、より詳細な確認事項が必要になっています。
ところで、宅地建物に関する不動産取引の重要事項説明と言うと、宅地建物取引主任者をして重要事項説明書の説明と書面交付を宅建業法で義務付けされていますが、今年の6月の国会決議で、平成27年度4月より「宅地建物土地引主任者」の名称を、「宅地建物取引士」と改める決議が採択されています。
一部の士業界からは、宅地建物取引主任者の名称変更に関して、全国で約90万人も現状の資格者のが居るし、不動産取引に携わっている者は約20万人で知識や資質にも大きなばらつきが有るので、全体の資質を向上させなければ、士号を付与する意味がないのでは無いかという疑問の声も有るようですが、私は決してそうは思いません。
その考えとはむしろ逆で、日本中で90万にもなった国家資格者だからこそ、土地建物に関する詳しい知識を有し、人の生死生存に関わる重要な取引に携わり或いはその当事者と為るわけでですから、さらに研鑽する動機付としても、今回の士号の名称変更は意義の有るものだと考えています。
勿論、従来の主任者の資格者をそのまま自動的に士号を付与するというのは手落ちだと思いますので、免許更新の際の講習時には、士号を付与するにふさわしい内容の研修を行い、また、協会団体で指導していくシステムを構築する必要も有ると思います。
私たちの、宅建協会と言う団体は、そんな意味でますます社会への公益に資する必要が有り、不動産事業で地域に根差す各会員が、その地域その立場持ち場で、「なるほどの人」と成れるように精進努力する必要を感じています。
自然環境の変化による水害やがけ崩れや津波等の災害や、原発廃棄物や科学工業廃棄物による環境汚染や土壌汚染の危険性が広がっている中で、過去を知り現在から未来に渡って知識を継承し、地域の住生活に関する安全・快適・資産としての様々な情報を提供して行けるのは、日々の地道な調査や聞き込み等の積み重ね蓄積が欠かせません。
宅地建物取引主任者(取引士)の本分は、試験に合格して終わりでは有りません。
むしろ試験に合格してからが、本当に社会に役立つ勉強の始まりだと思います。
参考
「取引士」に改称/宅建業法改正案/主任者の地位向上
http://www.kensetsunews.com/?p=30314

2014年08月31日
日本の人口は2055年には7千万に台になる?!。

厚生労働省平成24年発表の「日本の人口の推移」という統計グラフを見ると、1950年からの実績と2055年までの予測がよくわかります。
すでに人口減少の局面に突入していると云う事と、15歳から64歳の働ける人口の減少と65歳以上の高齢者人口の増加が如実に表れて、高齢化率を急激に押し上げています。
それでも、このグラフは出生率が現状維持出来た場合の希望的観測でしか有りません。私たち日本人がかつて経験した高度成長時代の成功事例のビジネスモデルやライフスタイルは、もう全て過去のもので有る事を再認識しなければなりません。それならそれで、その現実に即した方策を打ち出すしかありませんね。
日本の人口の推移を表したこのグラフは、日本全体の人口動向を表した表です。大都市圏と地方都市や田舎の人口推移はそれぞれに違いが有りますが、おおよそこの表の流れに近いものが有ります。ただ、地方や田舎に行くほど曲線の山型の前倒しが有り、大都市部ほど山形が右よりになっているという違いです。
と云う事は、総人口は変わりませんので、大都市部や地方中心都市においては山が大きく右よりになり、生産年齢人口の減少と高齢率の傾斜が急激なグラフになるようです。つまり大都市部や地方中心都市の高齢化率は、ちょうど新興住宅団地の急速な高齢化現象と似ています。
田舎の農村部や地方中心都市周辺部の地域は、すでに少子高齢化が進んでいますのでこのグラフより山が左寄りに偏っているイメージになります。したがって今後高齢化率の上昇はあまり急激に推移しないと思われます。
どちらにしましても、このグラフの曲線は、現在の政府が行っている政策が決め手となって、今後の結果が数値として表れてくると思います。人口の推移は国や自治体や各団体や企業にとって、経済的な問題に大きく影響します。それが巡り巡っては私たちの生活に、物価変動・収入・税金・福祉・公共サービスの内容の優劣として直撃することになる訳です。
生まれて来る子供の数と生産年齢層の成人と、それまで頑張って現役を引退し余生を過ごす高齢者層のそれぞれの人口比率が、微増減は有りながらも適度な推移をする事で安定することが、平和で暮らしやすい理想的な社会を維持する為の大きな要素だと思います。
近隣諸国との民族問題や領土問題等の様々な問題を抱えながらも、民主主義の先進国としてそれぞれに安定した政治努力を積み重ねて来た、西欧の国々の政治理念やライフスタイルに学ぶ事がまだまだ多くあると思います。
日本は残念ながら民主主義に付いては、現在のところまだ後進国だと思います。勿論日本には日本の独特な精神文化の良さが有りますので、その良い処は捨てることなく、西欧の政治システムの良いところを取り入れると云う事です。
人口減少と少子高齢化の問題に対応するという事に付いては、特に近代に人口減少を先に経験した北欧の国々の政治手法を学ぶべきだと思います。
間違っても、戦争の為の武器や原発を輸出して外貨獲得しよういう現在の政府の国策は、国を豊かにする政治でも何でも有りません。そんな事では、国際社会の中で孤立することになり、旧日本帝国や現在の北朝鮮の政治思想と似たりよったりの事になると思います。
内閣改造も行われる様で、一見一時期、政権が安定したように見える現在の日本ですが、こんな時こそ方針を誤るととんでもない方向に行きかねません。政権与党の自民党の議員の責任としては、時の内閣執行部をよく監督し、何としても大局を見誤らない鳥瞰の目と国民の痛みの解る虫瞰の目を凝らし、日本の未来に希望の持てる、国家国民の為になる政策を実行してほしいもものです。
2014年07月22日
【借金に追われて】日本が太平洋戦争に突入した理由が悲しすぎる【原発・靖国まで】
日本の国と、平和の事を考えている方だけお読みください。
17世紀以降の国際的な戦争は、政治的・経済的な近代化が遅れてしまった地域の民族紛争を火種に利用した、先進列強国の財閥貴族やユダヤ系富豪や、その手先になった政治家による、莫大な軍事マネーゲームだったわけです。
軍需産業の武器や、日本が人体実験場になった原爆投下もそうですが、現在も事故処理実験場となっている福島原発や再稼働を急いで知る川内原発も、もちろんそのマネーゲームの一環で高度成長時代に政治的に誘致された軍需施設の準備基地だと疑われます。これは、開発途上国が軍備強化を防ぐための列強国の軍事力の切り札でもあり、誠に危うい事ですが戦争抑止力とも謳われています。(あくまでも列強国に取っての抑止力という事で解釈できます。)
今まさに、世界中はヨーロッパでも中近東でもアジアでも、地域的な緊張が高まっています。いや、列強国間の経済的な都合で、意図的に緊張を高めている言っても過言ではないと思います。
日露戦争や先の世界大戦の終戦処理でも分かるように、日本が本当の平和を願望する国として自立する意思と決意を内外に示さなかったら、再びその列強のマネーゲームに巻き込まれて、その渦中で動かざるを得ない事は明白でしょう。ここはよくよく慎重な言動が、世界平和を目指す国家として必要とされる局面だと思います。(よもや日本が、列強の仲間入りをしていると勘違いしていると国が亡ぶと思います。)
国連が認めているという集団的自衛権というものは、そのマネーゲームに有利に突入するために、マネーの主導権を持つ列強国が好都合なルール―を作っただけです。日本は、ようやく国の近代化を明治維新で成功させた直後から、そのマネーゲームの餌食にされたことは間違い有りません。そしてその影響は現在でも続いているのです。
集団的自衛権の行使容認という国家像の根幹に関わる事を、正式な手続きを踏んだ憲法改正にもよらず、時の内閣の判断で行えるという決議を支持するという事は、人の命を懸けた戦争マネーゲームに参加出来るいう事を、一部の人任せにして容認するというものです。これこそまさに国民としての無責任行為だと思います。
どう好意的に弁解しようとしても、我が国の憲法に謳われている真の平和を目指す国家像としては、根本的にそぐわないものだと思います。
-------------------------------------------------------------
【借金に追われて】日本が太平洋戦争に突入した理由が悲しすぎる【原発・靖国まで】 ~NAVERまとめの記事より~
日露戦争で日本は、米国系ユダヤ人らから借金をして戦争を行い、「ロシアに勝利」しました。しかし、実際には、同じユダヤ人がソビエトに金を回し、ロシアの崩壊を誘導していたと言われます。そして、やがて太平洋戦争で米国に敗戦した日本ですが、太平洋戦争開戦時も日本は米国の借金を負っていました。
以下、NAVERまとめのサイトをご参照ください。
http://matome.naver.jp/odai/2136214578373977801
2014年05月21日
自然エネルギーを利用した再生エネルギー発電

最近、鹿児島は雨模様の天候が続いていますが、気温や湿度が比較的に低いので不快感が無く、まだ梅雨入りは先のように思えます。今朝は雲間から日光がさして明るい感じがします。こんな季節ごとの穏やかな地球の自然環境が、永遠に続いて欲しいものだと思います。
ところで、自然エネルギーを利用した再生エネルギー発電が急ピッチで開発されています。太陽光パネルの光発電や風車を使った風力発電が現在のところ有力で、現実的な実用段階に入っています。コスト採算的にも、初期投資が比較的に廉価になって、商業ビジネス投資の対象にもなってきました。
それによって、従来の大手電力会社による独占事業だった発電事業も、法律の規制が緩和されて来れば、民間の企業も参入出来るようになってきました。しかし、日本の場合はまだまだエネルギーシフトの理解が薄く、本格的な発電事業への参入には、電気事業法の規制や配電網の利権問題の壁が厚く立ちはだかっています。再稼働に躍起になっている、放射能汚染の危険性の大きい原子力発電の原子力ムラもその一つです。
さて、自然エネルギー開発の代表としては、地球上の自然の働きである、「火・水・風」と、太陽から届く「光」等が有ります。そのどれもが自然界の持つ特性として「変動と不安定」という問題点が有りますが、電力需要消費地域ごとにそれぞれを複合して、それぞれを補完し合って活用する方法が研究されています。
また、それぞれの独自の発電手法も、様々な新しいアイデアにより、より安定的なより効率的な手法が検討され、例えば風力発電一つを取っても、新型風力発電として様々なデザインの発電ユニットが開発されています。
https://www.google.co.jp/search?q=新型風力発電&lr=lang_ja&tbs=lr%3Alang_1ja&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=D_p7U-zfNoSGuASN2YG4DA&ved=0CEMQ7Ak&biw=1600&bih=775
そこで私が考えるには、風力発電だからと言って、何も自然豊かな山奥や海辺や海上にある必要は無く、例えば、都会の高層ビル群の谷間に強風が吹く場所が有るのなら、そんな場所を利用して風を集めて羽を回し、地下に設置したタービンを回すとか・・・、色々なアイデアがそれぞれのユニットの中にもあると思います。
そして、分野の違うそれぞれのユニットも、組み合わせ方のアイデアによって、安定性と経済性を十分に高めることが出来るのでは無いかと思います。
最も良くないのは、寄らば大樹の陰の様な強い物の味方的思考や、長いものに巻かれろの様な自己保身的な考えに、何時までも拘束されていることだと思います。
コロンブスの卵のように、それまでの常識に囚われない大いなるチャレンジ精神が、まだ人間の未熟な化学の知識では見えていない、大宇宙の真理を発見して行くんだと思います。
今、私たちが直面している地球環境とエネルギー問題は、まさにその扉の一つだと思います。
kiki*の東京タワーライブ 2014年05月18日 ustream.tvネットテレビ放送
鹿児島発、“2兄+1妹+2友”で結成された5人組バンド・kiki*がお送りするTV番組。
http://www.jujiya-music.com/
担当:野口099-239-8585
http://item.rakuten.co.jp/ontai/kiki/
2014年05月13日
すべて事実。実際に異変を感じている人たちがいる

「すべて事実。実際に異変を感じている人たちがいる」
「美味しんぼ」登場の医師 「すべて事実。抗議は被災者に失礼」
中日新聞 (2014年5月13日)
http://iryou.chunichi.co.jp/article/detail/20140513073049244
「美味しんぼ」登場の松井英介医師によると、原発事故が起きた当初から、実際に放射能による体調不良を訴えた被災者が大勢いたそうです。大きなどす黒い力の圧力に負けないで、真実を伝え続けてほしいですね!。
あの事故当時、放射能から逃れるために鹿児島に避難してきた方たちの話でも、現地に残った知人の中には、鼻血が出たり頭痛や吐き気で苦しんでいる人が多数いたと聞いています。
患者が症状を訴えて病院に行っても、原発や放射能との因果関係については良くわからないと言う事だったそうですので、カルテにも放射能が原因での疾患とは記録されていなくて、何人の人が放射能を原因とする症状を訴えて居たかを証明するのは不可能だと思います。それでも、遠く離れた鹿児島で聞いただけでも、被災地では相当多数の人が症状を訴えていたことは間違いないと実感して居ました。実際に現地に居た全ての人に聞き取り調査をすれば、たぶん800人どころではない多数の証言が出てくると思いますが・・・。
そもそも被災を受けていない人が、自分に健康上の被害が出ていないから実際に起こった被災者の健康被害を報じる事が「証拠がないから風評」だという理論でとんでもない批判を繰り替えしています。自分達に都合が悪いから迷惑だ!という理由で・・・。
しかも国の大臣や県知事や著名人やマスコミまでそれに加わって、作者に対するいわゆるバッシング同様の事を行っています。
体調不良の人の数が多少合わない事を問題にして、被害者の人数が少ないからそんなに問題にして騒ぐような事では無いと言う考え方や、被害に遭っていないその他の人の迷惑になるから被害者を表に出さずに隔離しよう言うような、まるでかつてのハンセン病隔離政策の様な事をすることは人権蹂躙ですし、今回の様な表現者の言論の自由の封じ込めを行うこと自体が、自由民主主義の思想破壊だと思います。
被害者がたとえ少数又は一人でも、しっかりと原因究明して事故が再発しないような対応をするのが、本当の民主主義では無いだろうかと思います。
私は、20年以上マンガを殆ど読んでいませんので、「美味しんぼ」というマンガも知識として知っているだけで、作家の名前もよく知りませんでしたが、是非今度読んでみようと思いました。何しろ、名だたる政治家や評論家やマスコミがこぞって批判したり話題にするほどですので、およそ只者では無いのでしょうね!。
2014年04月18日
大自然の中で生かされている事に感謝して・・・
あの未曾有の大災害、東北大震災から丸三年が経過しました。TVや新聞で岩手や福島県の現地の復興の様子を見ると、破壊された住宅や社屋の建物の瓦礫の片づけがようやく終わって、再建築や復興の兆しが見えてきています。Google(グーグル)地図のストリートビューでも、道路整備や建物の再建が行われたところが写っていて、生々しい災害の傷跡が少しずつですが癒されてきている感じがします。勿論それでも、実際に被害に遭われて大切な親族や住むところを失われて、災害避難仮設住宅や避難先にて悲嘆に暮れて居られる方も多く、その方々の心の傷跡は今後もそう簡単に癒されるものでは無いとは思いますが、荒々しい大地の巨岩をも侵食して形を変えていく水の流れのごとく、時間は容赦なく流れ去ってゆき、やがては人々の記憶をも侵食してそして人は自然へと帰って行くものなのでしょう。その地球上の自然環境が、人の営みによって大きく崩されようとしています。火を使う人間文明の発達によって、全地球規模で起こっている環境の変化は、二酸化炭素の排出と大気中への蓄積によってもたらされる地球温暖化の影響が、世界中の気候の変動や南北極地の氷の融解と海水位上昇として、至る所に顕著に表れてきています。それは過去の気象観測データが参考にならない程、著しい気象現象の変動をまねいたり、地震による津波の規模が潮位の上昇により起こる、べき乗的変動を起こす可能性が有り、過去の気象データや経験による想定をはるかに超えた災害となり得ることを忘れてはならないと言うことです。
人間にとっては触れるべきではない(これらは神様の領域であると思います)分野の、DNA操作や原子核分裂(融合)技術による生命やエネルギーの創造についても、同じことが言えると思います。人為的に引き起こされる変化は、もはや過去の経験値やデータでは、予想も付かない変化や取り返しが付かない結果をもたらす可能性が有る!ということを認識して取り扱う必要が有ると思います。
いずれにしましても、こんなにまでグローバル化した人類の地上の社会活動において、人間のおごり高ぶりや油断からもたらされる過ちの積み重ねは、自然界への直接的なダメージとして蓄積されていて、もはや早晩自然界の回復力の許容範囲を超えてしまいかねません。人間は何時までも身勝手な欲望に支配されるのではなく、私たち人間を始め多くの生命を育んでくれている、この母なる地球の大自然の中で生かされていることに感謝して、生類の互い助け合いと環境を守っていくことに、一人一人が出来るところから努力しなければならないと思います。
今年もまた例年のように冬が過ぎ、温かく光あふれる春が訪れようとしています。しかし、誰しも昨今の異常気象ともいえる自然環境の変化に気付かされていると思います。そしてその変化のスピードが、近年は徐々に早まりつつ有ります。本当に手遅れにならない内に、切り替えが必要な時期が到来しているのでは無いかと思います。
みなさんはどの様に感じておられるでしょうか?。
2014年03月06日
霧島市役所の方がいたら気を悪くしないで下さい。

昨日は、売買契約済みの中古住宅の住宅ローン審査の為、銀行に提出する資料として必要ということで、建築確認記載証明をもらいに、鹿児島県霧島市役所の建築指導課に出向いたところ、(組織的な問題だと思いましたので、名前までは公開しませんが・・・)これが今時のお役所仕事か!という様な、理解に苦しむ驚きの対応が2つ有りました。
(もしFB友達に、霧島市役所の方がいたら気を悪くしないで下さい。)
今朝、朝一番から相談の電話を掛けて、今から証明書を取りに行くと担当者に伝えて有ったのに、いざ窓口についてからの対応でも、役所側の保存記録に地番記載の間違いが有って、証明書が出せるの出せないのという事で押し問答になりました。
間違った記録だったら訂正したら良いのではないかと私が言うと、担当者は、「提出された記録の訂正は出来ません。」というでは有りませんか。
当時の確認申請の内容が間違っていたにしても、間違いをチェックするのが役所の仕事だし、記録を転載する時に間違いが起こることも有る訳ですので、なんで間違いを訂正することが出来ないのかが良くわかりませんでしたが、それならそのままで良いので、記録されている通りの証明書を出して下さいとお願いすると、ようやく何とか証明書発行にまで漕ぎ着けました。
霧島市役所の建築指導課は、本庁建物5階に有るのですが、証明書発行手数料200円をい支払うのに、本庁1階に有る提携銀行(JA農協)まで行って専用の納付書で支払いをして、納付書済証を持って、今発行した証明書を受け取りに来てくださいというのです。
1階に下りてからまた5階に書類を取りに行くというのも何とも不合理な話なので、「証明書と納付書を頂いて1階の納付窓口で払い込んで、納付済証を預けておくと言うのではいけないんですか?」と聞いてみると、「当役所の決まりなのでそれは出来ません。」との事。
申請人の名前と住所も記録しているのだから、そんな人を疑うようなことをしても仕方ないでしょう!。と言っても、「決まりですからの1点張りでした。白々しいその態度に少しカチンと来たので、「どこの役所でもこんな仕組みのところは無いですよ!。誰がそんな決まりを作ったですか?、その人と話をしたい!」と、強い口調で食い下がったら、上司らしい人が来て、「ご面倒をおかけしますが、やっぱり決まりですから・・・。」の1点張りでした。私の大声に、それまでがやがやしていた5回のフロアーが一瞬静まり帰って、大勢の視線を感じたので、ふと我に戻って、この人達に何を言っても仕方ないなぁ!と諦めることにしました。
次の約束もあり、説教している時間もなかったので、仕方なく急いで1階に下りて200円の手数料の払込みをして、また5階まで掛け上がって、ようやくA4用紙1枚の証明書を受け取りながら、「ちょっとこの仕組みは改善した方が良いですよ!。よく考えたらどうですか!。」と言い残して急ぎ足で帰りましたが、何だか釈然としない気分でした。
どうも、担当部署の窓口で小口現金を取り扱うと、収納に不備が出たり行く先不明金が出たりで不都合が有るらしい。いわゆるネコババでも有るのでしょう。一部の公務員の質が低下しているようで、何ともお粗末な話で管理する側には気の毒だとは思いますが、内部事情の都合の為に肝心の市民サービスが低下してしまっては本末転倒では無いでしょうか?。
今度、同市の窓口に行ったときに、こんな不合理な仕組みがその後どうなっているかを確かめてみたいと思います。
2013年10月14日
日本の国土利用と電力エネルギー生産に付いて思う

霧島市牧園町高千穂の売家を見に行く為に、牧園の町を通って高千穂方面に国道を走っていると、道路沿いの左側に太陽光発電施設が出来ていたので写真を撮りました。
最近は、幹線道路を車で走っている時に、新しく設置されたメガソーラー施設を発見することが有ります。少しづつは太陽光発電等のクリーンエネルギーの、安全性と長期的な経済的メリットが認識されるように成り、技術の進歩と共に益々増えていくと思います。
国道沿いの利用価値のない単なる斜面だった土地が、日当たりが良いという利点が有るだけで、発電基地として利用されて活かされていくことは大変素晴らしい事だと思います。
それならば、例えば農業効率が悪く働き手を無くして限界集落となってしまった、山村の耕作がされなくなった棚田や段々畑等でも、日あたりが良く道路のアクセスや送電設備がそれなり整っていれば、ソーラー発電基地として利用出来る土地が沢山有るはずです。
また例えば、日本の電機メーカーが優秀な日本独自のエレクトロニクスの技術を集結して、世界一効率の良い太陽光パネルを生産して国内で設置して実働検証する事もビジネスチャンスかもしれません。
その製品を大量生産して諸外国に輸出出来るとしたら、限界集落となった山村にも、太陽光パネルの生産工場を誘致して地元雇用をしたら、高度な技術経験者が定年後故郷に帰って田舎暮らしをしながら、適当な仕事に従事する様な労働力を得て、比較的低コストで生産性を高めることが出来るかもしれません。
TPP参加で、山間部の多い日本の国土の特性にとって、不利とされている農産物生産地のセーフティネットは、単に補助金を出せば良いというものでは有りません。日本独自の技術活用による新しいビジネスモデルの開発育成が欠かせないのだと思います。
そのためには、この際思い切った発想の転換が必要であり、2,000年以上も外からの文化を受け入れて国内で醸成させて来た、極東の島国日本に培われた独特の文化と自然感や人生観を大いに発揮するべきだと思います。
3.11東日本大震災により、福島原子力発電所の核燃料メルトダウンが発生しました。
原子炉建家の爆発事故と原子炉破壊による放射能漏れにより、原子力発電の放射能漏れの危険性や廃棄核燃料の安全処理が全く出来ない現状等・・・が一気に明るみに晒されてしまいました。
既に日本国内に54基も莫大な費用を掛けて建設されながら、危険性が高い為に取り扱いが難しく稼働率が極端に低い原子炉の維持管理コストの他、古くなった原子炉を廃炉にするコストや、使用済み核燃料の貯蔵や廃棄処分問題も全く解決出来ない状態ですので、現実的に原子力発電に電力を頼ることは不可能な事だと思います。
日本人は、昔から少ない資源を上手に活かして生活して来ました。何故日本国民に取ってエネルギー生産量でも極端に過剰で大変危険とも言える、54基もに上る原子力発電所を作る必要が有ったのでしょうか?。
何と!、世界中の原子炉の核燃料を日本で再利用して大儲けしようという、無知蒙昧で魑魅魍魎で浴深な大企業役員連中と、金のために政治を利用していた不得な悪徳政治家や、勉強不足で私利私欲で動いていた官僚達が結託した結果だったのです。今でもそんな人たちの事は「原子力村」の人々と呼ばれています。
ただし、それはその人たちが自分で思いついた仕組みでは有りませんでした。その頃、原子力先進国として、原子力発電を夢のクリーンエネルギーとして推進していた西側先進諸国でも、原子爆弾製造の後や原子力発電所や核燃料の廃棄物の処理に困っていました。
もし事故が有っても極東の島国日本なら、自分達にその被害が及ぶ危険が少ないだろうと考えて、核燃料再処理施設を建設するプランを、日本に売り込んだのは、アメリカ・イギリス・フランスを始めとする、その連合国だった訳です。
でも、核燃料再利用のプランは、核融合(現在の原子力発電は、比較的制御しやすい核分裂を利用して行われている)という現段階では発電エネルギーとして利用する為の制御について、理論的には可能だが技術的に開発出来ていない未来の技術によらなければ実現出来ないプランなので、世界中で原子炉が稼働する限り、原子力発電の燃料の燃えかすを何処かに保存して置くしか無いのです。
その保存場所を、日本は諸外国から引き受けるという約束をして、日本中に原子力発電所とその核燃料保存施設を作りました。でも、実際は核融合による核燃料の再利用は出来ない訳ですので、現在はその保存施設は日本中何処でも一杯になっていて、更に保存施設を何処にしようかと政府ぐるみで躍起になっているわけです。
原子力発電所が再稼働できない原因は、安全基準や活断層の問題では有りません。実は、原子力発電所を稼働したら、更に放射性物質を大量に放出する核燃料が更に増加してしまうからでも有るのです。
政府や電力会社は困った挙句には、地下に埋蔵するというプランを立てています。安倍首相が、原子力発電技術を輸出するという計画は、実は、原子力発電の技術を売り込んで利益を得ようというよりも、むしろ、使用済み核燃料の埋蔵場所を探すという意味の方が主なのでは無いかという懸念さえ有ります・・・。
どちらにしても、放射能とPPMは金輪際ゴメンですね!。
鹿児島発、“2兄+1妹+2友”で結成された5人組バンド・kiki*がお送りする番組。
「ジャスクリ」のインターネットラジオ番組、毎週金曜日更新!

kiki*のファーストアルバム「カテゴライズ」のCD購入は、
鹿児島市内天文館の十字屋CROSSさん、
十字屋CROSS http://www.jujiya-music.com/
十字屋CROSS 担当:野口
099-239-8585
http://item.rakuten.co.jp/ontai/kiki/
2013年08月07日
kiki*【宗義】たった一枚のCDができるまで。【写真と感謝】

(kiki* blogより)
夜分遅くにこんばんは。宗義です。
今回は長くなりますが、どうか最後まで読んでもらいたいです。
今日は記念すべきkiki*の1stミニアルバム「カテゴライズ」ができるまでを振り返ってみようと思います。
まず、アルバムを作成するにあたって、メンバーやスタッフと収録曲やコンセプトについて徹底的に話し合います。
(ここからはブログでご覧下さい。)
http://kiki-memorial.blogspot.jp/2013/08/blog-post_7.html?spref=fb
2012年08月27日
大隅の田舎にも、放射能の危機が忍び寄っています!
鹿児島に最終処分場???
 ↑写真は候補地としてあげられている、南大隅町辺塚エリア。
↑写真は候補地としてあげられている、南大隅町辺塚エリア。鹿児島の南大隅に福島で除染した放射能汚染土の最終処分場を造るというニュースが8月23日にTBS系列だけで放送されました。次の日の県庁前の原発反対のイベントでは、この最終処分場のニュースへの反対意見が次々と飛び出しました。僕は福島県いわき市の出身ですが、福島の事故からの放射性物質が付着した瓦礫や土やその他の廃棄物を、県外に持ち出して、処分の責任を他府県の人に押しつたいとは、これっぽちも思いません。多分、福島の住民の気持を代弁していると思います。しかし、福島県と国の政府は、放射能物質を全国に拡散させたいようです。
25日(土)に南大隅の自然を守る会がこの最終処分場計画反対の説明会を急遽開くという連絡を受けて、予定を色々変更して僕たちも南大隅町役場に行くことにしました。
財部町から鹿屋を抜けて根占港までは車で約2時間ほど。遅れて到着すると、80名程度の人が大きな会議室を一杯にしていました。
それぞれ、最終処分場への反対の気持ちを熱く語る中に、「遠方から応援に駆けつけてくれた人には恐縮だが、地元のことはまず地元で決めるので、よろしくお願いします。」という的外れな発言をする男性がいて????となりましたが、後から聞くとどうやら地元の推進派のよう。福島のあれだけの事故の後に、核や原子力が一度コントロール不能になると、「地元」などという小さな境界を大きく飛び越えて被害を拡散させるという事実をまったく理解できていないのだな〜・・・と驚きました。
でも、田舎に住む人の世界観は「地元」が思考の中での一番大きな枠になっている場合が多々あるので、しょうがないのかも?とも思いますが、その、最大で地元を考えることが精一杯の人たちに、原発誘致の判断を任せてきてしまったツケが、今、日本に50数基もの原発を存在させてしまった一番大きな要因であるとも考えられます。
この最終処分場計画への反対運動をするなかで地元の南大隅町を2分するようなことは避けたいですから、そうならない反対の方法を模索しなければ行けないのかな?と思いながら皆さんの話を聞いていました。
関係者から色々聞くと、最終処分場候補地になっているのは、太平洋側の辺塚というエリアであると言うことを教えてもらって、早速辺塚に向かいました。
南大隅町町役場がある根占から辺塚に続く県道563号線は、花瀬という美しい段々畑が広がるエリアを通って山道に入ります。ここには花瀬自然公園という観光地があり、その真ん中を流れる花瀬川の千畳敷の石畳は一見の価値があるところです。
563号線の山道の終点を右に折れて74号線に入り、しばらく南下すると辺塚漁港がある集落に着きます。船が4艘ばかりの本当に小さな漁港です。周辺の自然は手つかずの照葉樹林に囲まれた美しい海!豊かな海産物が目の前の海に沢山いる気配がひしひしと伝わってきます。
しかし、何でこんな処に漁港が?と思ったらちゃんと石碑が建っていました。
山中貞則という自民党議員が防衛庁長官時代に、近くに自衛隊の施設を造るので、その迷惑代としてプレゼントしてくれたものだと説明があります。まるで山中という議員のポケットマネーで造られたような書き方ですが、いえいえ、違いますよ!税金です、税金!! 残念ながら僕が住んでいる曽於市の出身・・・自民党はこうやって田舎の人々をてなづけて、原発を54基も造ることに成功したわけです。福島の事故ではまず自民党が謝罪するのが責任ある大人の対応だと思いますね。
この漁港、ざっと見た感じでは、今は漁業はしていないようなイメージでした。
で、これが、漁港を造る口実となった自衛隊の施設。佐多射撃場です。的になる断崖などが見あたらないので、海に向かって射撃をするのだろうと思います。
こんなへんぴな場所に、こんなに沢山の自衛隊の人がいます。近くにはヘリポートや宿舎もあるようです。
ここで地理的な条件を少し整理してみようと思います。
南大隅町は鹿児島の南端。種子島や屋久島を望む位置にあります。その自然資産のボリュームからみて、「九州の知床」と言っても間違っていないような場所です。赤枠が問題になっている辺塚エリアです。この部分を拡大してみます。
左下に辺塚漁港、その隣に、射撃場、右上に稲尾岳、射撃場と稲尾岳の間の急峻な山岳エリアが計画の候補地になっているようです。
同スケールで青森の六カ所再処理工場群をみてみると、候補地の辺塚エリアには充分な面積があることが分かります。地層処分での処理を考えているという説明もありましたが・・・除染土の受入を認めてしまえば、その後は、高濃度汚染物質、そして、廃炉後の汚染廃棄物、挙げ句の果てには使い残された燃料棒までが持ち込まれることになるでしょう。もし、何かが漏れ出せば、黒潮にのって日本の太平洋沿岸の漁業は壊滅です。そればかりか、九州を北上し、瀬戸内海、日本海へと流れ出ていく可能性もあります。
辺塚漁港の漁業権を買いあげ(多分簡単に買い取れるでしょう)、専用港を造り、道を整備し、労働者の宿舎を造り、処分場を建設する。これは土建屋にとっては喉から手が出るほど欲しい事業です。輸送関係も大喜び。情報筋によると、この周辺の土地の買い取りを進める動きもあるようで、下地整備は着々と進んでいるようです。
計画候補地となっている急峻な山間部には県道74号線がクネクネと蛇行しながら20km先の船間という集落まで続いています。いったいどんな山なのか74号線に踏み入れてみると、その道は県道とは思えないほどの細さと整備状態。切り立った崖の縁をクネクネと進んでいくような道です。途中、打詰(住人は10人以下と思われる)という集落の脇を通り、肝付町に入って、辺塚海岸に出るまで、1時間以上の山道、すれ違った車は1台。人の気配はなく、僻地の中の僻地。こんな場所がまだあったんだと思うようなエリアです。海岸に降りていくような林道すらありませんでした。急峻な山、ゆえに開発や利用の余地もなく、今回のような処理場建設候補地にはうってつけの条件だと思います。町長も県知事も、あの場所から数十億単位の税金を毎年永遠に巻き上げられるのであれば!と考えると心が揺らぐと思います。しかし、今のところ、そうはしないと両人は公言していますが、田舎の町長の発言など、まったく信用できないし、官僚下がりの伊藤知事の発言はとっくに信頼がおけません。法的な担保が必要になってくると思います
辺塚漁港をさらに南下すると本土最南端の佐多岬にでます。写真は佐多岬の展望台から薩摩富士と呼ばれる開聞岳を望む様子。海が美しい!周辺の山々も熱帯性の植物が生い茂り、逞しい自然の美しさを見ることができます。
こちらが佐多岬、太平洋に向かって伸びていく様子が美しい岬です。霧島錦江湾国立公園に指定されています。
現在は青森の六カ所に押しつけている核廃棄物の問題は、今後、僕たちが原発廃炉とともに、熟考して解決策を生み出していかなければならない課題だと思います。一般的に有害な廃棄物には「管轄エリアを越境しない」という大原則があります。例えば、国際法では、有害廃棄物の輸出入は厳しく規制されています。(バーゼル条約)。同様に有害どころか毒物、もしくは劇物である放射能に汚染された土、瓦礫、廃棄物も、その廃棄物を発生させた、都道府県から外に出すことを禁止すべきだと思います。そして、それぞれの原発の敷地内で処理・保管ができる方法を開発するべきです。もともと、ハイリスクハイリターンを承知の上で、原発誘致を行ったそれぞれの「地元」が責任を取って、残った燃料棒までも管理するのが正論だと思います。
その為には、県条例として「放射能物質越県禁止条例」を制定し採択する方法もあるのかな、と思います。鹿児島県であれば、川内原発から出る放射能物質や放射能に汚染された廃棄物は県外に持ち出さない。川内の原発内で処理保管を行う。しかし、県外からも一切持ち込まない。そういう条例です。
持ち込ませない条例は過去にも幾つか例がありますが、それではフェアーではありません。持ち出さない、持ち込まない。これをセットで立法化できれば説得力があると思います。しかし、問題は、現在原発を抱える自治体が運営破綻した場合です。この際には「東京都が保管する」という附則を記載しておけばいいのではないでしょうか?
今までの「自治体の放射性廃棄物拒否条例」は下記リンクから参照できます。
れんげ通信 by 市民ネット・岐阜 http://www5b.biglobe.ne.jp/~renge/jyoeiindex.htm
この記事は、ブログ「山のツバル」より転載しています。
2012年08月13日
マスコミに載らない海外記事

我々は、核のもたらす生命の危機に付いて本当に考えなければなりません。
もともと核は、電気エネルギーの問題では有りません。地球生命体の健全な存続に関する問題だったのです。核エネルギーの問題は大宇宙の神様から、地球上の私たち人類に与えられた最大で最後の命題なのかも知れません。
それはもう、使い方の問題ではなくて、使うべきか使わざるべきかの二者択一の問題です。つまり無に帰するか、有を続けるかの問題だと思うのです。
もう長く考えている時間は有りません。最終的な実験の結果は、世界中で全て現れているのです。特に原発大国日本では、今後更に顕著に現れてくるでしょう。
「マスコミに載らない海外記事」
福島第一: 原子力発電所から核兵器第一へ
2012年6月13日 Veterans Today Anthony Hall
http://eigokiji.cocolog-nifty.com/blog/2012/08/post-2cc5.html
※注意↑上のリンク先ページには、ショッキングな画像が幾つか含まれています。開くときにはご注意ください!。
“我々の世界は、これまで想像されたことのなかった危機に直面している… 解放された原子の力が我々の思考方法以外のあらゆるものを変えてしまった為、我々は未曾有の大惨事へと押し流されつつある”
アルベルト・アインシュタイン、Bulletin of Atomic Scientists(原子力科学者会報)、1946年5月
アルベルト・アインシュタインの警告と福島第一原発の不吉な運命~
2011年11月01日
心とデスクマットの模様替え

おはようございます。今日は11月の初日で、いよいよ今年もあと二ヶ月になり本年度最後の追い込みの時期になりました。震災・津波・原発・洪水・不況・円高・クーデターなどと今年は何かと暗いニュースが多かったのですが、こうしてブログを書いたり見たり出来る私達としては、何とか無事に過ごさせて頂いている事に日々感謝して、毎日を明るく陽気に頑張って行きたいと思います。
先日家内のアイデアで、何十年も和ダンスの奥に眠っていた、家内の和服の帯をこわしてデスクマットにしてくれました。目から入る明るい色彩が、なんだか心も明るくしてくれるようで気に入っています。着物の帯は長いので、同じ柄で応接テーブルのテーブルマットや椅子のカバーにもなっています。少しの工夫で私の事務所兼書斎が随分明るい雰囲気になりました。
私たちは誰でも、それぞれの心の中に人として最も大切な、周囲をを明るく照らすことが出来る前向きな明るい心や、人を助けることが出来る暖かい心を持っています。ところがそれを心の奥の引き出しにしまいこんだままにして置くと、いつの間にか引き出して使う事がだんだん無くなって、しまいには何処にしまったかも分からなくなってしまいます。
大切な物事は、常日ごろから表に出し言葉に出したり行動したりする事で、色あせる事も無く益々輝きを増してきますので、物を惜しまず身を惜しまずに出していけるようにしたいものだと思います。
時折、身の回りの一寸した模様替えをしてみるのも良いものですね。
2010年09月01日
我がふるさと鹿児島が国際化するために

~「我がふるさと鹿児島が国際化するために」~
牟礼岡団地に有る、私の自宅兼事務所の6帖の畳部屋には、パソコンデスクとコピー機やプリンター等の事務機器や書類ラックが、ところ狭しと並んでいます。パソコンデスクの左側には床の間があり、娘の雛祭りに買った2体の雛人形のガラスケースの横には、私の母親が長男の2歳の誕生日に買ってくれた古びた地球儀が置いてあります。もう28年前の安物の地球儀なので、国の名前や都市の名前があちこち違っているし、回してみると心棒の所が壊れていて、ガタガタ音を立てながらいびつな回り方をするような代物ですが、何となく捨てるに捨てられなくて、今でも懐かしい思いで時々眺めています。
子供たちがまだ小さかった頃は、よくこの地球儀を親子で囲んでは、国の名前と首都の名前を当てるゲームを遣ったものでした。また、TVで外国旅行などの特集番組を見た後は、この地球儀を持ち出して番組で紹介していた旅のルートを辿っては、まだ見ぬ広い世界に旅のロマンを感じていました。
さて今日は仕事の合間に、ふとその地球儀を手に取り回しながら見ていたら、日本を取り巻く中国大陸と東アジアの国々が、身近な国だという実感が湧いてきました。特に鹿児島は、歴史的にも中国大陸や東アジアとの交易や交流に深い関係があり、黒潮に乗って運ばれるアジアの文化を受け入れてきた特徴が有ります。地域の産業や農産物にはその特徴が良く現れていて、古くは米の品種が伝わり米食文化が始まった事や、新しくは唐芋や焼酎の伝来も鹿児島から始まったようですので、歴史的に食と文化の南方からの玄関口に成っていたことは間違いないと思われます。また幕末には、西洋の文化を逸早く取り入れ、明治維新の立役者として日本の近代化に貢献したのも、鹿児島の薩摩藩でした。
現在の日本は、終戦後の奇跡的な経済復興を成し遂げた後に、高度成長期を過ぎてバブルが崩壊し、経済も政治も自信を失い混沌としています。少子高齢化による教育と福祉の問題や、政権交代後の政局不安定や、膨れ上がる財政赤字など、どれも内向きの問題ばかりがクローズアップされてしまって、積極的な外交対応や経済対策が後手後手の状態となっています。これでは高度成長期に突入した大国中国や、それに続くアジアの発展途上国に次々と置いて行かれるのが落ちです。
現在の日本の状態は、天下泰平の江戸時代の末期状態に良く似ています。自民党独裁の太平の時代が長く続いた結果、激しい時代の変化に付いて行けない体質を作ってしまいました。これではいけないとようやく気付いて政権交代を行ないましたが、政権が変わっても国の体質そのものがまだ変わっていません。民主主義国家に於ける国の体質と言うのは、誰の事でも無く官僚を始め国民一人ひとりの物の考え方と行動規範が作り上げるものですので、政権政党が変わろうと首相大臣が変わろうと五十歩百歩だと言えなくも有りません。
だけど、諦めてしまっていては全て終わりですので、こんな時代だからこそ私たちがやるべきことが有ると思います。あの幕末の時代の国家の危機と内政不和で混沌とした時代に、鹿児島の薩摩の志士達が取った行動というのは、がむしゃらに諸外国に学ぶことを行なったわけです。それは、技術や経済だけでなく、物の考え方を学ぶ事が大きかったわけで、そのことが封建社会の日本を自由民主主義の国に変えていく力にも成ったのだと思います。私たちが今やるべきことは、かつて薩摩の志士達が行なったように、胸襟を開いて外国の文化に学ぶ事だと思います。
日本人がアメリカの傘下の元、高度成長を成し遂げて一夜の春を謳歌し、ゆとり教育や完全週休二日制などという甘えの構造を制度化して、大人も子供も腑抜け状態にされていた頃、近隣アジアの国々の中には、厳しいながらもこつこつと努力を続けてきた国が有ります。そんな国はどこでも語学教育に力を入れていて、自国語は勿論のこと英語と中国語を必須の語学科目として取り入れ、3ヶ国語を自由に使いこなせる人材を育てています。
一昔前までは、2ヶ国語が話せる「バイリンガル」が必要な人材といわれていましたが、今では3ヶ国語が使いこなせる「トライリンガル」が、国際社会においては最も必要とされる人材になっているそうです。それは、ただ外国語が話せるとい事だけでなく、他国や他民族の考え方を理解出来るという点で、すばらしい調整能力や交渉能力が身につくという効果が有るからだと言われています。
私も五十の手習いの言葉通り、英語と初めての中国語の勉強を始める事にしました。また、語学教育に関心を向けて、外国人と実際の会話が出来る、発音重視の語学教育への取り組みが必要だと感じています。その他、外国人語学留学生の受入が出来る住環境の整備にも取りかかりたいと思っています。個人負担を軽減できる「シェアハウス」や「ルームシェア」は、金銭的負担軽減のメリットだけでなく、他国文化の人とシェアする事でお互いが学びあえると言うメリットが有ります。この事は仕組みを作ることで不動産の仕事にも繋がると思います。
幸か不幸か、国内の長引く不況下の中で、近隣アジア諸国の経済成長と日本の対外国政策の緩和で、日本国内への外国人旅行客や留学や移住者が増えているそうです。時代は否が応でも異国文化と触れ合う事を余儀なくさせているようです。地理的に中国や台湾・東南アジアに近く、気候的にも過ごしやすい鹿児島の風土は、アジア圏の観光地としてや、医療・教育・食量・文化の中心地として発展する要素が充分に有ると思います。
ただ、そこには成否を分ける要素として、受け入れる側の住民の体質が大きく鍵を握っているような気がします。今後の鹿児島がどのような地位を築き、発展していくのか衰退していくかは、その地域に住む住民の体質による総意によって変わっていくものだと思います。その中から民意を得た優秀なリーダーが沢山育って、鹿児島の素晴らしい未来を作り上げて行く事を信じたいものです。
随想-平成22年8月12日執筆-
平成22年9月1日 メールマガジン「土地と建物の関係」に掲載
【ご意見・ご感想フォームのバナーリンク】
続きを読む
2010年07月17日
「地球温暖化と異常気象」・今週発行したメルマガ原稿です。
●今年の梅雨は、やたらと激しい雨が至る所で降り続きますね。今までも、集中豪雨と言う呼び方で呼ばれていましたが、どちらかと言うと台風の進路に沿って大雨が襲ったり、年度によって地域が変わったりという形で、どちらかと言うと季節や年回りのサイクルのようなものが有りました。
ところが今年は、南から北まで日本列島をすっぽりと覆うような形で、ゲリラ戦のような断続的な集中豪雨が至る所で起こっています。気象科学の専門家は、今年の春まで続いたエルニーニョの影響で、偏西風のひだが中国大陸から日本列島まで大きく南に下がって蛇行している事が原因では無いだろうかと言うことです。
冷たい大陸高気圧と、暖かい湿潤な太平洋高気圧の谷間が丁度日本列島の真上でぶつかり合って、山岳地方を中心に大量の激しい雨を降らせているという分析のようです。
なるほど、日本で大雨が起こっている原因は何となく判りました。でもその偏西風の湾曲やエルニーニョの原因になっているのは何なんでしょう?。日本の異常気象は、すなわち地球規模の世界の異常気象と密接な関係が有ると考えられます。
原因については様々な説が有るようですが、最も信憑性の高い説はやっぱりなんと言っても、地球全体の気温上昇による様々な異変が上げられています。
地球温暖化といわれる現象そのものは、惑星サイクルの中では大した変化では無いのかも知れませんが、かつては海や陸が有ったらしいと思われる火星の砂漠化した現在の姿を考えると、地球の環境も何れはそうなる危険を含んでいると考えるのが自然です。
地球の自然は、窒素と酸素と微量の二酸化炭素やその他のバランスで大気が構成されて守られています。その大気が、太陽光の直射日光を適度に遮ってくれたり、自然の断熱材として昼夜の気温差を適度に和らげてくれたりと、生命が存在できる環境を作ってくれています。
ところが、創世記の地球は惑星内の内部火山活動が活発で、水蒸気を含んだ炭酸ガスを大量に噴出し、二酸化炭素を80%も含んだ炭酸ガスの大気で覆われていて、高温で生命体の存在しない惑星だったそうです。
徐々に地球の内部活動が沈静化すると同時に、水蒸気が太陽のエネルギーで水素と酸素に分化され、水素と酸素は炭酸ガスの雲で発生した雷による電力の科学反応で結合して、水に変化し大地に降り注ぎ地上の海となりました。
地球は地軸が傾いていることで、太陽の周りを公転する事により起こる南北の日照量の変化が大気と海洋の奇跡的な対流を起こし、海と空との間で何度も何度も、降雨と蒸発を延々と微妙な変化を繰り返しながら規則的な歩みを繰り返しました。
そのことから、「火と水と風」と言う生命にとって必要な働きが理想的なバランスで作りこまれたのです。やがて地上の海に光合成でエネルギーを作り出せる生命体が大量に発生し、大気中の二酸化炭素は海とやがては陸の植物に取り込まれて、何代も間の永い年月を掛けて地中に固定され続けて来たのです。それが、石炭や石油と言うような化石エネルギーになったのです。
また一方で、二酸化炭素は植物とは別の進化を遂げた、動物生命体の骨や肉体の等の材料にも成ったのです。かつて動物は死ぬと他の動物に食われて、食った動物の肉体となりました。また、食われなくても土に返り、植物の養分となりまたそのまま大地に定着しました。
生命体の自然淘汰のバランスは、地球環境のバランスを保つ上で密接な関係が有ります。地球の平均気温と、植物や動物の生命体のバランスについていは、一見無関係に見えることでも、実は密接な関係が有るようです。
(ここのところは説明が長くなるので、次のページをご参照下さい。)
海と大気の生成と循環⇒ http://park5.wakwak.com/~ryo-tai/sub2.htm
とにかく、地球環境は私たちが考えているよりもデリケートな一面を持っています。それは、地球の平均気温が1度上昇すると海水が60C上昇すると言われていますが、南極・北極の氷が溶ける事だけでなく、大量の海水の体積が海水温上昇により膨張する為だと言われています。
表面だけの海水温上昇だけの内はまだ良いですが、深海まで温度が上がり始めると話は深刻です。予想を上回る海水上昇だって有るかもしれません。
現在のシュミレーションでは、50年後には地球気温が3~4度上昇する可能性が有ると予測されています。と言うことは、水位が最大2.4m上昇するかもしれないと言うことです。
そうなると平野部の海抜の低い場所は、海岸に近い所は勿論ですが、河川が近い所は相当上流部分まで、高波や高潮の影響を受ける危険が有ると言うことです。人間の安全は勿論、農作物や漁業等への影響は計り知れないものになると思います。
また、それだけ気温が上昇すると、ますます気象状況が変わって来ます。局地的な豪雨はますます激しさを増し、また一方で局地的に激しい旱魃(かんばつ)に見舞われます。例えば、今年は大雨でもう雨はこりごりだと思っても、来年は空梅雨で台風も側を通らないと言う年になるかも知れません。
また、地球の平均気温は上昇したといっても、それは地表のことに過ぎません。はるか上空のマイナス何十度と言う冷気団はやっぱり北極上空に渦を巻いていますので、気流の変化による偏西風の蛇行や寒気気流の立ての変化が大幅に起こったときには、大寒波が襲ってくることも有ります。
見事にバランスが取れているものほど、一度バランスが崩れてしまうとエントロピーが増大して、何れは一気に臨界点に達してしまい、極度の変化が瞬間的に訪れてしまうことは良く知られた現象です。
そうならないためには、人間が出来ることとしては出来るだけバランスを崩さないように努力するしか有りません。また、不幸にしてそうなった時に対応できる、何らかの対策を講じて置くことが必要です。
そこで、私たちが全体の為に今すぐ出来る事は、二酸化炭素排出を抑える為の生活習慣に切り替えることです。それは省エネであったりエコライフであったり、生活コストの無駄を省きエコに役立つ機能にコストを掛けることも大事です。
そして、私たちが自分や家族の為に計画を立てて出来居る事は、生活と仕事の拠点を出来るだけ安全な所に移動することです。なるべく低地の海岸や河川の近辺を避けて、又、高地でもがけ下やがけ上、扇状地の山すそのくびれた場所等も避ける事です。
市街地でも、河川の中須地帯が開発された場所は危険です。地表はコンクリートで覆われていても、地下では地下水の巨大なトンネルが出来ている場合があります。
単純に仕事や交通買い物の便利さだけで、安易に住まいの場所を決めるのは危険です。また、どうしてもそのような場所に住まう必要が有るなら、それにはそれなりの対策を講じて置くべきです。
何れにしても、世界的な異常気象は既に始まっていますので、「今まで大丈夫だったから」と言うのは通用しない新しい時代に来ています。自分や家族を守れるのは、結果的に自分達の決断しか有りません。
地球温暖化と異常気象と言っても、地球にとってはほんの少し風邪をひいた位の事で、それほど案じることは無いとは思いますが、大自然の一寸した変化は、地球上の私達のような小さな生き物にとっては、抗いがたい大きな出来事でもあります。
毎年、夏も近いこの時期になると思うことですが、台風や水害が日本の何処かで大切な人の命を奪っていきます。天災は忘れた頃にやって来ると言われていますので、今まで大丈夫だったところでも、危険のネタが有る以上要注意です。
今後はますます異常気象の影響が、地球上の各地に現れてくる可能性が有りますので、国内外問わず御気をつけ下さい。海、山、川の水の集まるところにはくれぐれもご用心です。
【参考】(文部科学省作/自由探索コースがとても良く出来ています)
「地球温暖化を阻止せよ」
⇒ http://rikanet2.jst.go.jp/contents/cp0220a/start.html
本編は以上です。
今年の豪雨災害で被害にあわれた犠牲者の方のご冥福をお祈りいたします。
2010年05月20日
口蹄疫感染はグローバル化社会の問題提起

大きくなってきた飼い猫のキキ(今日の記事とは関係有りません。)
昨日発行したメルマガの記事を転載します。
以下、「土地と建物の関係」これがマイホームの夢と知恵袋 http://archive.mag2.com/0000072843/index.html より
~「口蹄疫感染はグローバル化社会の問題提起」~
●昨今宮崎では口蹄疫感染問題で大変なことになっています。TVでは感染が大幅に拡大したゴールデンウィーク明け頃から報道が始まって、今週はどのTV局もその話題がトップニュースになっています。
宮崎県では、今日現在で口蹄疫感染の恐れの有る牛や豚の殺処分が、約20万頭以上も指示が出ていて、対象に成った畜産農家の方々にとっては断腸の思いだと推察します。一日も早い終息が望まれる所ですが、今後の行方は「神のみぞ知る」と言う事でしょう。
発症当初の県の対応の遅れや、その後の国の対応が迅速でない等の批判が出ていますが、今は責任問題を追及している時期では無くて、感染の広がりをくいとめる方策をどのように的確に打っていくかと言う事と、被害に合った畜産農家の救済を検討する時期です。県や国が一体と成って迅速な対策を講じる事が不可欠な事です。実態に即した、縦割り行政では無い包括的な対処と意思決定を行なって欲しいものだと思います。
さて、丁度去年の新型インフルエンザの時と同じ発症時期に重なっていますが、去年の新型インフルエンザ(豚インフルエンザとも言われた)の時は、メキシコから感染が拡大した2~3月頃から始まって、4月には日本でも報道と告知が大々的に行なわれていた記憶しています。また、5月始めには香港や韓国でも感染者や発症者が次々と出て、5月中旬には日本でも感染者が確認され、アメリカやヨーロッパなどの世界中で感染者が見つかり、短期間のうちに地球全体に広がっている事が報道されました。
ここのところ経済圏のグローバル化が進み、人の動きや物流についても十数年までは考えられなかったようなスピードと、めまぐるしい勢いで地球上を駆け巡っているような印象があります。確かに交通が便利に成り、自由に多くの国々を行き来できるようになりましたが、国際間のハザードが低くなり流通や交流が自由になった分だけ、疫病やテロや戦争や経済破綻などの問題が発生した時に、一気に世界中に広がると言う別の危険性が多くなりました。
止め処も無く巨大化していく生命体や企業や組織は、いずれ破綻して絶滅を迎えてしまうと言うことを、私はこのメルマガで何度も書いているのですが、まさに今回のこともその事を示唆していると思えてなりません。
何故人間は人種や言語の違いが有るのかと言うことや、何故自然界の生物は何万もの種に分かれたのだろうかと言うことを考えてしまいます。
単細胞生物から始まり生命体の固体までも成長した生物も、誕生と死を繰り返しながら、自然界と調和し続けて生かされて来たわけですので、集散と住み分けとのバランスが崩れた時に、かつて無い激しい変化が起こって来ます。
人の社会も同じ事で、近年のグローバル化の影響が至る所に現れだしたものだと思います。経済や人の流れのグローバル化と、人・物・金の一極集中が対極に有り、当然のごとく結果として問題を起こしています。
また、それぞれのハザードが極度に引き下げられ、良くも悪しくも障害が無くなるということは、自由でもあり危険でもあり・・・。
まるでセキュリティーの無い家で、玄関の鍵を掛けずに住んでいる様なものです。田舎や未開地の原住民には当たり前の生活も、都会のど真ん中で生活するには危険すぎる行為であるように、自由でグローバルな生活を求めることは、危険との隣り合わせを受け入れるものでも有ります。
個人的には、田舎暮らしをお勧めしたり、田舎暮らしを体験する意義を全ての人にお伝えしたいと言う私の信念は、この口蹄疫感染拡大のニュースを見ながらも、ゆるぎない物となっているのです。
いずれにしても、情報網も交通網も世界中の国がお隣さんと言う時代を迎えて、自国だけの検疫体制や水際防疫では間に合わない時代が来たと言うことでしょう。安全保障や経済問題だけでなく、気候変化や疫病や地球環境の問題など、対岸の火事では済まない時代がやってきたと言うことです。
これからは、自国民の安全と幸福の為には、積極的に隣国を救済し共に生かされる道を作っていく事が、先進国家の役目で有り条件でも有ると思います。いわゆる、グローバル化した社会の問題点でもありますが、それはむしろ、グローバル化した社会における与えられたチャンスでも有ると思います。この機会に日本の国を挙げて、危機管理対策をしっかり行なえる仕組みを作る必要が有ると思います。国政の政治家はわが党やわが選挙対策だけに奔走すのではなくて、国家国民の一大事に対応する機能作りに命を燃やして欲しいと思います。
また各地方の首長である県知事連は、いずれ道州制に移行することを見据えて、各地方の実情に即した福利厚生を中心に、地元地方の経済圏の安全と発展の為に、近隣県知事連による行政の指導力を強化し、今回の口蹄疫発生のような地域的な一大事の時に連携して、包括的な安全対策をいち早く打ち出せる様な体制作りを推し進めて欲しいものですね。
続きを読む
2009年03月21日
居室も定員もずさん、火災「たまゆら」が群馬県提出の書類

今回の記事も、NPO法人の普及が必要だと説く「犬とレストランとイタリア料理」からすべて転載しました。NPO法人の正しい運営と真の目的追求の為には、関連法の整備や運営する為の人材教育などが急務なようです。今こそ日本でも円熟した社会構造を取り入れて、今後向かうべき未来像が必要なかもしれません。エコノミック・アニマルからヒューマンに進化するべき時が到来でしょうか?。
--------ここから転載記事------
2009年3月21日
居室も定員もずさん、火災「たまゆら」が群馬県提出の書類―NPOがもっと大きな活動をできるようにすべき!!
居室も定員もずさん、火災「たまゆら」が群馬県提出の書類
(この内容すでにご存知の方は、この項は読み飛ばしてください)
群馬県渋川市の高齢者施設「静養ホームたまゆら」で19日夜に起きた火災で、重傷だった男女2人が死亡したと21日、渋川署が発表した。
2人は東京都墨田区の紹介で入居し、延焼した別館にいた。火災の死者は男性5人、女性4人の計9人となった。
一方、たまゆらを運営するNPO法人彩経会(高桑五郎理事長)が県に提出した「運営内容確認表」は、居室25、定員25人としながら、図面では居室が15となるなどずさんな内容だったことが分かった。
彩経会が3日に県からの要請で提出した確認表によると、施設の概要では「居室数25、定員25人」となっている。ところが、建物の規模・構造では 「居室は1人室×15室」となり、建物の平面図も15室だった。また、施設は別館を含めて3棟あったが、「建物の規模」には、平屋建て215平方メートル とあるだけだった。
入居者については1月1日現在で24人となっていた。火災の発生時に施設にいた入居者は16人だった。
たまゆらは1996年4月の開設。渋川広域消防本部によると、施設は当初60平方メートルだったが、約450平方メートルに増えている。増築を繰り返していたとみられる。
近所に住む女性(38)は、「約10年前にホームを建設して以来、頻繁に施設を広げていった。最後にできた建物(別館)は掘っ立て小屋のようで、雑な造りだった」と話す。
渋川署の発表では、新たに死亡した2人は、相沢英男さん(88)と山田ヒデさん(72)。残る7人の身元確認を進め、21日も現場検証し、出火原因を調べている。
墨田区によると、相沢さんは区内のアパートで独り暮らしだったが、認知症になり、2007年2月に生活保護を申請、たまゆらに入居した。山田さん は08年7月に生活保護を申請。認知症などで要介護とされ、08年9月に入居した。群馬出身で、区の担当者に「ふるさとに戻れてよかった」と話していたと いう。
NPOがもっと大きな活動をできるようにすべき!!
このような、事件がおきて非常に残念なことだと思います。このNPOの場合は、悪質というより、活動自体が良く管理されておらず、杜撰でさえあったことが事件につながったのだと思います。
この施設にも、東京墨田区に居住していた人が入居していたようですが、最近このような事例が多いようです。墨田区でも、独居老人の住処が問題となっており、もうほとんど入居できる施設がないため、他県の施設を紹介することも多くなっているそうです。このような状況になると、墨田区のような立場の地方自治体ではなかなかチェックもできないようです。
しかし、中にはもっと悪質なNPOも存在していて、最初から生活保護費が目当ての悪質な業者もいるようです。そんな施設では、業者のほうが生活保護費をとりあげて、受給者をまるで劣悪なところに押し込め、まるで牢獄のようにしていているところもあったそうです。
とんでもないことです。NPOはもともと、社会問題を扱うセクターなのに、今のままではまるで、犯罪や、搾取の温床のようなものになってしまう可能性が大です。この「たまゆら」のNPO法人の代表や、悪質な業者を特殊な事例であると考えたり、攻め立てるだけでは何も解決しないと思います。まずは、行政などの監視システムをもっと強固にすべきです。
私が思うに、やはり、もっとNPOが大きな活動ができるように、まずは、税制を改革して、企業、個人がNPOに寄付すると、大幅に税金などが免除されるような優遇措置をつくるべきだと思います。また、NPO自身も税金などが免除されるだけではなく、様々な恩恵があるようにすべきと考えます。さらには、寄付だけではなく、NPOで無償で働いた人々に対しても減税や、その他の恩恵があるような、日本独自のシステムもつくるべきではないかと思います。
そうすることにより、もっと多くの人がNPOの分野に入ったり、新規で立ち上げたりできるよう支援していくべきだと思います。この火事にあった、施設も、もし資金が十分にあり、また、ボランティアで働いていただける人たちがたくさんいれば、こんなことにはならなかったのではないかと思います。それに、同じ社会問題に取り組んだとしたら、NPOは政府や地方自治体の1/10のコストで、10倍の速度で問題を解消していくと思います。
老人の問題、いずれは自分たちの問題にもなります。それに、たとえば、年老いた親がいた場合に、その介護をしなければならないので、仕事をやめざるを得ないなどということもあります。そんな場合、まともな施設があれば、安心して預かってもらうこともできます。それに、自分が年老いたことを考えてみてください。だれだって、まともなところに入りたいし、できれば、わが子や孫とと一緒に暮らしたいと思っているはずです。それがかなわなくても、少なくとも、しょっちゅう会える環境にありたいと願っているはずです。
ここでは、老人問題などを扱いましたが、ほかにもいろいろ問題があると思います。託児所の問題とか、子育てとか、教育、医療とか、雇用の問題、うつ病、無差別殺人などの重犯罪など手付かずの社会問題は山ほどあります。
欧米とは違い、日本には残念ながら社会問題解決のセクターとしては政府しかありません。欧米ではそのために、十分に機能しているNPOがあるのに、日本では、上記のような弱小NPOがほとんどです。これでは、非常に不安です。残念ながら、政府がこうした問題に取り組むと、全国一律で実施することになり、本当にサービスが必要な人には、何も提供されることがなく、必要もない人に手厚いサービスが施されるということになってしまい、非効率なことになってしまいます。だから、もし、政府がこうした問題に関心持って、支出を多くしたとしても、それだけでは社会問題の多くは解決しません。その多くが無駄遣いになってしまうことは、今では皆さんがご存知のことだと思います。
その点、欧米型の良く考えて構築されたNPOの場合は、効率がよく、小回りがきき、地域の住民のニーズにこたえています。このへんは、日本がこれから学ばなければいけない重要なところだと思います。こういった問題に真正面から取り組むことができる、有力NPO、これからの日本では絶対に必要になってきます。さらには、上記のようなNPOの活動を監視するNPOも必要になってきます。
また、こうした社会問題が解決されるか、あるいは将来解決がつくという期待感がなければ、いくら金融的な手段を講じたり、財政出動をしたとしても、なかなか景気は回復しないと思います。このブログでも、従来から述べているように、日本の経済力はかなりのものであり、ちょっとやそっとでは本来は不景気になるはずがないです。しかし、マイナス5%成長などといわれるのは、内需拡大がなかなかなされないことが原因だと思います。
内需拡大がされない背景としては、日本ではなかなか社会問題が解決される見込みがないと、多くの国民が思っているからだと思います。すべてがすぐに解決される見込みがないにしても、いずれは解決される、解決するように努力しているセクターがあるというだけでも、安心感が増して、内需が拡大していくと思います。日本の政治家や、官僚も、もっと社会問題をそうして、その社会問題を実際に解消していくプログラムや、システムなどに関心を持ってもらいたいものだと思います。 <Yutaka Yamada >
【関連記事】
------ここまで------
※田舎暮らしに興味が有る方は、参加してみませんか?。
良い田舎暮らし「土地と建物」その条件とは?
住まい情報メールマガジン「土地と建物の関係」無料購読!
鹿児島田舎暮らし日記 ⇒ 鹿児島田舎暮らし下書き帳
鹿児島の賃貸ブログは ⇒ 鹿児島・不動産賃貸ブログ
鹿児島の不動産は ⇒ 鹿児島の不動産情報「三伸ホーム」
鹿児島のロックバンド ⇒ メジャーに挑戦!!「天玄」(てんもと)
インターネットTVは ⇒ 鹿児島インターネットテレビ
鹿児島のコーポラティブハウス ⇒ セットスクエアー
ママと子供の情報サイト。 ⇒ 鹿児島でママライフを!「かごママねっと」
2009年02月25日
1ドル70円台の日本経済:三橋貴明(作家)の近未来小説(1

うえは海外カタログの写真。円高は、私にとっては良いことづくめだ。海外カタログをみていると、向こうでは金融危機の影響で、30%ディスカウントは当たり前なので、さらに円高でかつてと比較すると考えられないくらいいろいろな高品質なものが安く手に入る。しかし、海外カタログなど気軽に入手するひとはあまりいないだろうから、まだ、円高メリットを享受できる人は限られるのだろう。
1ドル70円台の日本経済:三橋貴明(作家)(この内容すでにご存知の方は、この項は読み飛ばしてください)Voice2009年2月21日(土)10:00
超円高で経済破綻?
「79円50銭です! 79円50銭を付けました。史上最高値が、ついに更新されました!……繰り返します。ロンドン市場で、円が1ドル79円50銭まで買い進められ、1995年に付けた円の最高値79円75銭を上回りました。95年以来、じつに14年ぶりに円相場が最高値を更新したのです! 昨年から予想されていたように、超円高時代の到来です!」
雨はいまも降りつづいている。
7月に入ったにもかかわらず、長梅雨は一向に終わる気配を見せない。
最近の新聞やテレビでは、契約を打ち切られた派遣社員の話題で持ち切りである。明日はわが身だ。中堅クラスの商社に勤めて、はや30年になろうとする自分だ。この年で解雇などされると、さすがに再就職もままならないだろう。梅雨が重い。湿気を帯びた空気が全身に纏わり付いてくる感触に、山本は2度、3度、何かを振り払う動作を見せた。
「ただいま……」
口元から漏れ出た声があまりにもうつろに響き、山本はわが事ながら思わず皮肉な笑みを浮かべたものである。それほどの疲労は感じないのだが、声色はごまかせない。玄関脇の傘立てに重さを増した傘を突っ込み、顔を上げると、リビングの扉から薄明かりが漏れ出ているのが見えた。
(……帰っていたのか)
山本は口元に歪んだ笑みを張り付かせたまま、リビングルームへと足を向けた。
「あ、父さん。お帰り!」
50インチを優に超える大画面液晶テレビから目を離さずに、息子の和仁が声だけで出迎えてくれた。その口調は若者特有の快活さに満ちていて、山本の眉間に微妙に皺が寄った。大学に入学したばかりの息子は、いつも陽気な態度を崩さない。むろん陰鬱な顔ばかり見せられるよりはマシだが、日々の仕事で気が休まる暇がない身としては、いささか忌々しく感じるのも確かだ。5年ほど前に妻に先立たれ、いまは息子と2人暮らしの父子家庭だ。山本はソファに乱暴にビジネスバッグを放り出すと、何げなくテレビに目を向けた。
瞬間、山本は背筋が凍りつく思いを味わったのである。画面の上部に「79円50銭!」と極太のテロップが浮かび上がり、中年の脂顔の男がヒステリックな口調で繰り返している。
「79円50銭です! 史上最高値が更新されました!」
この脂顔のアナウンサーの名前は、たしか古林といったか。悲観的なニュースを嬉しそうに語るそのスタイルが、山本は個人的に大嫌いだった。
「超円高時代到来か……」
山本は搾り出すように呟き、続けようとした。これで日本経済はおしまいだ、と。ところが山本の台詞は、妙に明るい口調の息子に遮られてしまったのである。
「良かったね、父さん」
「な……」
唖然とする父親に向き直り、和仁は目を輝かせながら続ける。心の底から嬉しがっている表情である。
「通学にバイクを使っていると、やっぱりガソリン代がきついんだよねぇ。これだけ円高になれば、ガソリンの値段もそうとう下がるはずだよね」
「あのな、和仁……」
山本は声音が荒々しさを帯びないように、注意深く語り掛けた。未成年とはいえ、自分の息子がここまで世間知らずだと、さすがに腹立たしい。
「円高の意味を分かっているのか? 日本経済が、これまで以上に大変になるということだぞ。下手をすると、経済破綻だ。いや、この調子で円が上がっていけば、間違いなく破綻するな」
「どうして? これまでの歴史上、通貨高で経済破綻した国は、1つもないよ。その逆、つまり通貨暴落で経済破綻した国は山ほどあるらしいけど」
息子の淡々とした口ぶりに、山本はかなり面食らった。いきなり「歴史上」などという返し方をされるとは予想していなかった。山本はネクタイをわずかに緩め、疲れた素振りで椅子に腰を下ろした。
「歴史上の話はそうかもしれないが、なにしろ日本は世界最大の外需依存国だ。このまま円高が続くと、輸出が不可能になってしまう。外需に頼る日本経済は輸出ができなければ、破綻するに決まっているだろう」
「外需依存国?」
息子の目が面白そうな光を帯びた。山本は何となく不穏な気配を覚えたものだ。
「何、それ? 日本が外需依存国って?」
山本は大きく溜め息をつく。こんな基本からいちいち説明しなければならないとは、わが息子ながら呆れたものだ。自分の会社の若手社員もそうだが、若い奴らはどうしてこう、常識というものを知らないのだろうか。
「外需依存国ということは、つまり日本経済が輸出に頼っているということだ。GDP、国内総生産に占める輸出の割合が、とても大きいという意味だな。だから円高になれば、日本は経済破綻に追い込まれるわけだ。分かるか?」
「輸出の割合が大きい? 輸出依存度、つまり輸出対GDP比率が高いってこと?」
山本はギョッとし、思わず異星人でも見るような視線を息子に送った。「輸出対GDP比率」などという、専門的用語が息子の口からすらすら出てくるとは、かなり違和感がある。山本は何となく焦った素振りで、少し早口に言い返した。
「そうだ。輸出対GDP比率が高いということだ。日本は外需依存国だからな」
「日本の輸出依存度って、せいぜい15%だけど、これって高いかな?」
「……高いだろう。15%もあるのだから」
「でも他の国と比較すると、日本の輸出依存度は、主要国のなかではアメリカの次に低いよ。なにしろ製造業が衰退しちゃった、あのイギリスよりも低いんだから」一瞬、山本は返す言葉を失った。何と反論してやればいいのだろうか。父親の戸惑いになどまるで気付かぬ様子で、和仁は滑らかな口調で続ける。
「ついでにいうと、主要国で輸出依存度が高いのはドイツや中国、それに韓国ね。なにしろこれらの国の輸出依存度は4割近くにまで達しているから、日本の倍以上だよ。日本が外需依存国というのであれば、ドイツや中国は何と呼べばいいんだろう。超外需依存国でいいのかな?」
「……」
山本は少し考え込んだ。具体的な数字を出されるのは予想外だったが、自分は筋金入りの商社マンだ。日々、さまざまな客先で、円高に苦しむ輸出製造業のサポートを続けている。彼ら輸出製造業の苦しみを、ダイレクトに肌で感じつづけているのは、息子ではなく自分だ。「数字上はたしかにそうかもしれないが、実際にこの超円高で、日本の輸出企業はたいへん苦しい思いをしているんだ。このまま円高が続くと、日本の輸出産業 は全滅するとさえいわれている。父さんは、毎日毎日お客さまとお会いして、直接お話を聞いているのだから、輸出企業の皆さんの厳しさはよく分かっている」
「父さん。実質実効為替レートって知っている?」
また知ったかぶりか。山本は、一瞬、激高しかかった自分を必死に抑え込む。まったく聞きかじりの半端な知識で、父親である自分に対抗できるとでも思っているのだろうか。「当たり前だ。アメリカドルだけではなく、日本と関係がある国や地域の為替レートを貿易量で加重平均して算出した為替レートのことだ。それがどうした?」
「いまの父さんがいった定義で算出されるのは、名目実効為替レートだよ。名目実効為替レートは、関係国の物価水準の変動を加味していないから、輸出の厳し さを正しく測れない。どれだけ名目実効為替レートが高くなっても、相手国の物価がそれ以上に高騰しちゃえば、輸出はかえって楽になるんだから。
日本の輸出企業が厳しくなるのは、物価変動を加味した実質実効為替レートが上昇したときね。もちろんいまは名目値の円レートが高くなっているから、実質実 効為替レートも上昇しているよ。でもいまだに130ポイントにも届いていないんだから、せいぜい2001年レベルでしかないんだよ。なにしろ1995年に 1ドル80円を切ったときは、実質実効為替レートが160ポイントを超えたから、あのときに比べれば、いまはまだ円安なんだよ。それで本当に輸出産業が全 滅とかいう話になるの? 日本の輸出企業って、そんなに弱いのかなぁ。信じられないよ」
たしかにそうだ。実質実効為替レートでいえば、いまはまだ2001年ごろの水準にすぎない。仕事柄、山本はもちろん現在の実質実効為替レートの水準を知っ てはいたが、日頃の業務のなかで「円高、円高」といわれるので、とくに何の疑問も抱かず、そのまま受け取っていた。しかしあらためて考えてみれば、 2001年レベルの為替水準で、日本の輸出産業が全滅などありうるはずがない。
⇒ 2)に続く。
2009年02月25日
1ドル70円台の日本経済:三橋貴明の近未来小説(2
2)内需は絶望的という大嘘
「しかしだな……」
山本はもはや必死に頭を振り絞り、息子への反論の糸口を探したものだ。
「実際、マスコミや経済評論家は、日本の内需は絶望的だ。だから日本は輸出で成長していくしかない、と毎日のように繰り返しているじゃないか。内需が成長 しないなら、やっぱり輸出で食っていくしかないわけだ。実質実効為替レートの件はともかく、いずれにせよ円高は輸出企業にとっては望ましいことではない。 なにしろ日本の内需はまったくダメなわけだから、頼みの輸出を順調に成長させるためにも、円安のほうが良いに決まっている」
「マスコミや評論家って、それって『〇経新聞』のこと?」
息子は笑いをこらえるふうに、肩を震わせている。何がそんなにおかしいのだ。父親に対してこんな態度をとるなんて、最近の若者ときたら……。いや、自分が和仁の年齢のころも似たようなものだった気もする。どうだっただろうか? 山本は不意に、自分の年齢を強烈に意識した。
「まあそのマスコミが何新聞でもいいけど、いまの話って、因果関係が逆だよ」
「因果関係?」
「そう。だって、内需がダメだから輸出で成長していく、つまり円安のほうが望ましいというけど、内需の成長が抑え込まれているのは、そもそも円安だったか らだよ。円が安くなっているときは、日本人の購買力がどんどん削られていっているわけだよね。輸入価格が上昇するわけだから。日本人の購買力が小さくなれ ば、国内を主な市場としている中小企業だって、それはやっぱり経営的に厳しくなるでしょう。外国への輸出で稼いでいる大企業はともかく、円安になれば中小 企業の収益力が落ちて、内需の成長率が低下して当然だよ。
内需を成長させたいなら、方法は単純だと思うけど。円高にすればいいんだ」
「円高にすればいいって……簡単にいうな。そもそも日本の内需、とくに個人消費は規模が大きくないのだから、円高で個人の購買力を強くしても、高が知れているだろう」
息子は何か言いかけたが、すぐに口を閉じた。ようやく言いくるめることができたわけだ。山本が取り戻した父親の威厳に、ホッと息をついたところ、
「父さん、それは本気でいっているの? 日本の個人消費の規模が小さいって……」
再び、何となく嫌な予感が込み上げてきたため、山本は押し黙った。父親の沈黙を受けて、和仁は寂しそうな視線を送ってきた。その眼差しには明らかに哀れみの情が浮かんでおり、山本の不愉快度は急角度で上昇した。
「本気だとも。経済新聞だけではない。テレビでも経済評論家がいつもいっているじゃないか。日本の個人消費は絶望的だ。だから、これから伸びることが明らかな新興経済諸国、たとえば中国などの市場に注力しなければならないんだってな」
「個人消費は日本のGDPの56%を占めるよ。日本のGDPは、半分以上が個人消費なんだ。それはもちろん、個人消費が7割近いアメリカには負けるけど、 個人消費がGDPの3割程度しかない中国なんかとは、比較にならないほど大きいんだよ。しかも中国の個人消費はGDPに占める割合が年々減りつづけている けど、日本のほうは逆に増えているよ。昨年にしても、あれだけ不景気だ、不況だってマスコミが悲観論をばらまいたのに、日本の個人消費はそれなりに成長し ていたんだよ。もちろん円が高くなって日本人の購買力が高まったのが原因だと思うけど」
「……」
「だいたい、父さん。マスコミや評論家が何かいうときに、数字を使って説明するのを聞いたことがないでしょう。数字を出すと嘘がばれちゃうから、みんな 『日本は外需依存国』とか『日本の内需は絶望的』みたいな、印象論だけを何度も繰り返してミスリードしているんだよ。なにしろ、世界に外需がゼロの国はな いから『日本は外需依存国』だってけっして嘘ではないし、円安のせいで日本の内需の成長率が輸出に負けていたのは確かだから、『日本の内需は絶望的』も嘘 とは断言できないからね。かなり、ぎりぎりだと思うけど」
「……」
「ついでにいうと、超が付く外需依存国である中国の純輸出(輸出-輸入)、つまり外需ね。外需がGDPに占める割合は10%近いんだよ。純輸出がGDPの1割近いって、ここまで外需に頼りきっている国はほかにはないんじゃないかな。逆に日本の外需、つまり純輸出がGDPに占める割合は、2%未満だよ。つまり日本のGDPは、じつは98%以上が内需なんだよ」
「しかし、日本は少子化で人口が減っているんだ。人口が減っているのだから、内需がこれから伸びるわけがないだろう」
「人口が減っているって……」
和仁は呆れたふうに、1つ大きく溜め息をついた。
「たとえば、昨年は日本の人口が5万人ぐらい減ったみたいだけど、それって日本の人口の0.04%にも満たない人数だよ。誤差レベルにも達しない人口が減って、内需がそんなに影響を受けるはずがないでしょう。
日本のGDPの半分以上が個人消費だから、日本に住む人が1年間に2%だけ消費を増やせば、それだけでGDPが1%増えるんだよ。どう考えても、人口よりも個人の消費の影響のほうが大きいでしょう」
「凄いな……」
さすがに敗北を認めざるをえず、山本は思わず口に出して呟いた。
「いったい、どこでそれだけの知識を身に付けたんだ。学校か。よくもまあ、それだけ具体的な数字がポンポン出てくるもんだ」
父親の賞賛の言葉に、和仁はやや照れくさそうな笑顔を見せた。
「大学で勉強したのもあるけど、やっぱりネットかな」
「ネット? まさか、インターネットのことか?」
思わず顔をしかめた山本に、またもや息子は寂しげな視線を送る。だから、その哀れみに満ちた顔はやめてくれ、と、山本は心の奥底で叫んだ。
「父さん。まさか、いまどき『インターネットは便所の落書き』なんて時代錯誤なこと言い出したりしないよね。ネットの世界では、不特定多数の見知らぬ人を 相手にするわけだから、きちんとした情報ソースに基づいて話をしないと、まったく相手にされないよ。だいたい父さんだって、会社でインターネットは活用し ているでしょう」
「……」
「ちなみにGDPや輸出依存度なんかのデータは、日本政府のホームページに掲載されているよ。たしかGDPが内閣府で、日本の輸出入が財務省。それに実効 為替レートが日本銀行のホームページだったかな。データを載せてくれるのはいいけど統計によってバラバラの場所に置かれているのは何とかしてほしいよね」
(政府のホームページからデータをもってきているのか!)
山本はかなり驚愕し、思わず言葉に詰まった。何というか、時代も変わったものである。これまで自分は、統計情報を調査するときに政府の一次ソースをきちんと確認したことがあっただろうか。ちょっと記憶にない。
「しかし日本が外需依存国ではないことも、円高が内需拡大に有効なことも分かったが、それならば政府は内需拡大に的を絞った景気対策を打てばいいんじゃないのか? これほどまでに簡単な話なのに、なぜやらないんだ?」
「やっているじゃん。昨年の12月に40兆円規模の景気対策を打つって発表して、きちんと予算を通したから、すでにいろいろな対策が始まっているはずだよ。マスコミがあまり報道しないので、状況がよく分からないけど」
「40兆円!」
山本は息子の話の内容よりも、金額のほうに衝撃を受けた。
「財政破綻寸前の日本が、40兆円もの景気対策を打つのか! そんなことしたら、瞬く間に財政が崩壊するぞ!」
「あははははははっ!」
いきなり息子が腹を抱えて笑いだしたので、山本は危うく反射的に怒鳴り散らすところだった。何がそれほどおかしいのか、さっぱり分からない。というか、父親の威厳はどこに消え失せてしまったのだろうか。自分が何か、とても大切なものを失った気分だ。
「ざ、財政破綻って、日本政府が? よ、よくもまあ、それだけ滅茶苦茶な話を信じられるね。あははははっ」
「いったい何がそんなにおかしいんだ」
「だ、だって、父さん、マスコミに毒され過ぎだってば……。ああ、面白かった……はあ……」
ようやく息を継ぎ、息子は涙目の笑顔を見せたものだ。
「あのね、父さん。日本が財政破綻するとか、あれ、嘘だから」
「嘘……?」
「そりゃ、嘘でしょう。日本政府の債務はたしかに巨額だけど、95%以上が国内向けの国債、分かりやすくいうと日本国内の民間からの借り入れなんだよ。つ まり円建ての債務ということになるよね。円という通貨を発行できる政府が、円建て債務のせいで財政破綻するわけがないでしょう」
「しかし、夕張市は財政破綻したぞ。ほかにも危ないといわれている自治体はいっぱいある」
「当たり前だよ。夕張市は紙幣発行権があるわけじゃないんだから。夕張市が日本円を刷ったら、普通に犯罪でしょう」
いわれてみると、たしかにそうだ。夕張市と日本政府を一緒にすることには無理がある。
「財務省が掲載している日本政府のバランスシートを見ると一発で分かるけど、日本政府の債務、つまり負債は840兆円もあるけど、同時に資産もでかいんだ よ。なにしろ政府の金融資産だけで550兆円近くもあるんだから。これだけ巨額の資産をもっている政府は、世界中にどこにもないよ。債務額から金融資産を 差し引いた純債務額で見れば、日本の政府の債務はGDPよりも少なくなり、普通の先進国並みになるよ」
山本は言葉を失った。そういえば、借金の額にばかり目が行って、政府は資産ももっているということに考えが及んだことは1度もなかった。
それはそうだ。山本は心中で同意した。
「日本政府の債務のほとんどは、さっきいったとおり日本の民間から借りているんだよ。ということは、政府の債務はそのまま日本の民間の『債権』ということになる」
「マスコミは『国民1人当たりの借金』といって危機感を煽っているじゃないか」
「あれもひどいミスリード、というかインチキ・レトリックだよね。正しい言い方に改めるならば、『国民1人当たりの政府に対する債権』になるよ。だって、借りているのは政府であって、国民じゃないからね。国民はどちらかといえば、貸しているほうでしょう」
「……」
「だいたい国債を買っている人たちは、資産運用として国債を保有しているわけだから、償還するといわれても逆に困ると思うよ。国債が償還されても、みんな 結局また国債を買う羽目になるに決まってる。日本国債以上の安全資産は、この世に存在しないから。だから、日本政府は国債の償還期日が来たら、同額の国債 を発行して永遠にロールオーバー(借り換え)していけばいいだけ。日本国内に国債の買い手がいるかぎり、日本政府の債務規模は問題になるわけがない。しか も日本の家計の金融資産が1400兆円を超えている状況だから、日本政府が国債の買い手に困るなんて、ちょっと考えられないと思うよ」
⇒ 3)に続く
2009年02月25日
1ドル70円台の日本経済:三橋貴明(作家)の近未来小説(3
世界経済への義務を果たそう
「うーむ……」
山本は思わず唸り声を上げた。国債を買っているのは誰だ? こんな基本的な疑問を、これまで考えたこともなかったのは、なぜだろうか。
「それにさっきもいったけれど、日本政府は通貨発行権をもっているんだよ。いざとなれば、日本政府は日銀に日本円を発行させて、国債を買い取らせることも 可能なんだ。だから日本政府が財政破綻など、現実にはありえないよ。アメリカがいま、FRBにドルを増刷させて米国債を買い取らせているけど、あれと同じ 事をすればいいだけだから」
何というべきか、山本は自分のこれまでの常識が根底から覆される感覚を覚え、呆然とした思いで言葉を搾り出した。
「それでは、政府の債務が800兆円を超えていようが、40兆円の景気対策を打とうが、大した問題ではないのか」
「それはそうでしょう。景気対策が順調に行なわれて、名目成長率が上がれば、政府債務のGDP比は勝手に小さくなっていくもの。それよりも、とくに財政危 機でも何でもないのに、景気対策を打たずに内需拡大の機会を逃すほうが危ないと思うよ。さっきも父さんがいったとおり、円高で輸出企業が厳しくなっている のは、紛れもない事実なんだから」
息子が一瞬、皮肉とも受け取れる笑みをこぼした気がするが、気のせいだろうか。
「まあ、輸出企業が厳しいのは、円高よりも世界的な需要の縮小のほうが原因としては大きいと思うけど、だからこそ、世界中の政府が財政支出をして景気を下 支えしようとしている。そんなときに、日本だけが何もしないわけにはいかないよ。なにしろ円高という日本の内需に対する絶好の追い風が吹いているんだか ら。
だいたいサブプライム危機やリーマン・ショックで、主立った国はみんな借金頼みの不動産バブルや株式バブルが崩壊して、内需がボロボロになってるんだ。そ んななかで、幸運なことに日本の内需はそれほど痛めつけられていないうえ、もともと規模が世界で2番目に大きいんだよ。内需を拡大させて、輸出よりもむし ろ輸入を拡大して、世界経済復活のために貢献する。これこそが世界経済に対する日本の義務であり、いま、日本がやるべきことだと思うよ」
山本はもはや心の底から感嘆し、降参の意を込めて両手を軽く上げた。
「おまえの年齢で、経済についてそこまでしっかりとした考えをもっているとは。正直、父さんは感動した」
完膚なきまでの敗北だったが、なぜか山本はすがすがしい気分を味わっていた。息子は恥ずかしそうにいったん顔を伏せ、何も言わずに晴れやかな笑顔を見せた。
翌朝のこと。
いつものようにテレビのスイッチを入れた山本の目に、いきなり古林の脂顔が飛び込んできた。
「また、こいつか……」
山本は思わず声に出して悪態をついてしまった。
古林はまるで苦行僧のように顔を歪め、嫌そうな口ぶりでニュースを読み上げている。昨日のヒステリックな態度とは、まるで別人のようだ。
「……繰り返します。内閣府が本日発表した前四半期における日本のGDP、国内総生産は、輸出の大幅な落ち込みを個人消費の増加がカバーし、若干のプラス 成長に終わりました。全般的に輸入価格が下落したことや、ガソリンが1リットル100円を切ったことなどが、消費を下支えした模様です……」
どう考えてもよいニュースだと思うのだが、古林の口調はいかにも悔しそうで、山本は思わず声に出して笑ってしまった。
リビングの大きな窓に目をやると、眩いばかりの陽光が差し込んできている。雨は上がったらしい。
そういえば、もうすぐ夏がやって来る。
なぜ世間知らずの大人が増えたのか?
この内容については、私自身も前から手を換え、品を換え、このブログでも主張してきたことです。でも、この内容さすがは、作家が書いたもので、包括的にしかも誰にでもわかりやすく書かれていると思います。だから、全文をそのまま掲載しました。
この文書の一番最後の、「眩いばかりの陽光が割きこんできている。雨はあがったらしい。」に関しては、この作家の予測ですね。日本の遅れていた景気回復が、梅雨どきには、そろそろ気配がみられ、夏には完全に回復基調になっているということだと思います。
私自身もこのブログでも、かねてから主張してきたように、おそらく5月くらいからは、景気回復の気配がみられるようになり、9月頃には回復していると思います。
今の日本の現状は、欧米より少し出たしが遅れたということであり、日本の実体経済は欧米のように悪くはなっていませんから、日本が一番先に回復するどころか、しばらくすると内需景気に沸いてくると思います。
上の文書でも触れていましたが、日本は昔から経済は、内需依存型です。そのため、もともと国際競争力も他国と比較すれば、高くはありませんでした。わずか、10年以上前までは、GDPに占める輸出の割合は8%以下でした。この10年間で倍の16%程度になっていますが、それとて、他国と比較するとアメリカに次いで低いです。だから、日本は、今でも輸出大国ではないし、過去もそうだったことは一度もありせん。というより、日本は内需大国です。
アメリカがサブプラムローンや、GMの金融小会社がやった車のローンのように、信用のない人にまで貸付するなどして、無理やり消費拡大をしなくても、十分可能です。
日本のマスコミなど、ごく一部の現象を極大化して見せてたり、ごく短期間のできごとを長期間にわたって続くことを平気でやります。これに関してはこのブログでも何回も主張してきたことです。
経済に限らず、環境問題でも、そのような傾向が見られます。環境問題に関しても、マスコミはいろいろな不確かな情報を拡大して流します。これに関して、私は大学生の時に貴重な体験をしました。これに関しても、以前このブログに書きましたが、これに関しては、まだ読んでいない方は是非ご覧になってください。その頃的確なアドバイスを聞かせてくださった大学の先生には、今でも感謝の念で一杯です。そうでなければ、私もいわゆる世間知らずの大人になっていたかもしれません。
ここまで、読んでいただいた方は、世間知らずの大人とはどういう意味かもうお分かりだと思います。これだけの情報化社会になったにも関わらず、マスコミのいうことに関してなんら批判的な観点ももたず、一方的に信じてしまうような大人のことです。いまでは、インターネットも普及していますから、自宅からでも、会社からでもふと疑問に思ったことは、調べてみれば、相当なところまで、短時間で確かめられます。あまり重要なことでないことで、労力を費やす必要はないとおもいますが、自分の仕事や、生活に直接関わる事柄に関してわずかの労を厭うようでは、お話にならないと思います。
にもかかわらず、それをしないで、マスコミの垂れ流す情報をそのまま信じてしまう人。これが、私の言う「世間知らずの大人」というところです。上の文章に出てくるお父さん、まさにこのタイプですね(笑)。最近では私は、バチカン報道のおかしさを掲載しましたが、あの一方的な中川元大臣バチカンご乱行報道など、ただ鵜呑みにしてしまう人も結構多いのだと思います。私の陰謀説など信じなくても良いですが、中川元大臣を取り巻いていた人の中には著しく配慮に欠ける人がいたのではないかとか、マスコミの一方的な報道には少しおかしいと思ってもらいたいです。
それに、マスコミにも「世間知らずの大人」が多くなったのではないでしょうか?特ににマスコミで不足していると思うのは、「現代世界史」の分野です。高校だと、あまり受験に関係ないことと、世界史でも、年度末に近い頃に教えるので、あまり教えていないのかもしれません。
大学では、学問の分野が専門化するため、教養の時代に世界史などとらなくてもいいわけですから、興味のある人だけが選択する。そうなると、マスコミや外務省に入るような人でも一生知らないで過ごしてしまうということがあるのかもしれません。私も、有名大学を卒業している文系の新卒の人が「ゴルバチョフ」を知らないというのを知って、少なからずショックを受けたことが何回かあります。
以前ブログ界でも「ナチス、ソ連」といっても通じない若者たちが増えているということが話題になっていたことがあります。逆に、このへんのことでも、何でも情報通の若者も増えています。まさに、二極分化しています。
しかし、これは若者だけではなく、上の文章にでてくるお父さんの世代も同じことだったのかもしれません。ただし、お父さんの世代には、インターネットなどが普及していなかったので、気づかれないですんでいただけだと思います。
ここで、若者だろうと、壮年層だろうと、道は二つに分かれると思います。若者層には将来「世間知らずの大人」にならないために、すでに「世間知らずの大人」になってしまったお父さんたちにも、マスコミで報道された事柄をそのまま鵜呑みにしないで、必ず裏取りをするという習慣をつけることです。こういった習慣を身につけるかどうかで、その後の人生は大きく異なってくると思います。そうして、最大の違いは、裏取りをする習慣を身につけた人は、「自分自身の人生を自分自身で選択して送ることができる」ということです。そういう習慣を身に着けなかった人は、たとえ経済的に恵まれようが、なんであろうが「他人の考えに従属し、自分自身の人生を他者の選択」でしか送れなくなってしまいます。
できたら、なるべく客観的な数字にあたるということだと思います。さらに、それも一箇所だけではなく、なるべく複数の数字をあたるということだと思います。さらに、数字で表せないような情報に関してこそ、なるべく多方面の情報を仕入れることだと思います。
上の文章のお父さん「最近の新聞やテレビでは、契約を打ち切られた派遣社員の話題で持ち切りである。明日はわが身だ。中堅クラスの商社に勤めて、はや30年になろうとする自分だ。この年で解雇などされると、さすがに再就職もままならないだろう」と述べていますが、「世間知らずの大人」を続けていたら、こうした運命をたどる率はかなり高くなると思います。裏を取る習慣がなかったら、会社の仕事も失敗だらけになると思います。もし、こうした運命をたどったとしても、景気のせいや、人のせいにはできないと思います。自分が一番悪いということです。
さて、若者諸君、君たちはどっちの道を選ぶのかな?
以上
Funny Restaurant 犬とレストランとイタリア料理
より転載しました。
⇒ 最初から読む